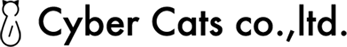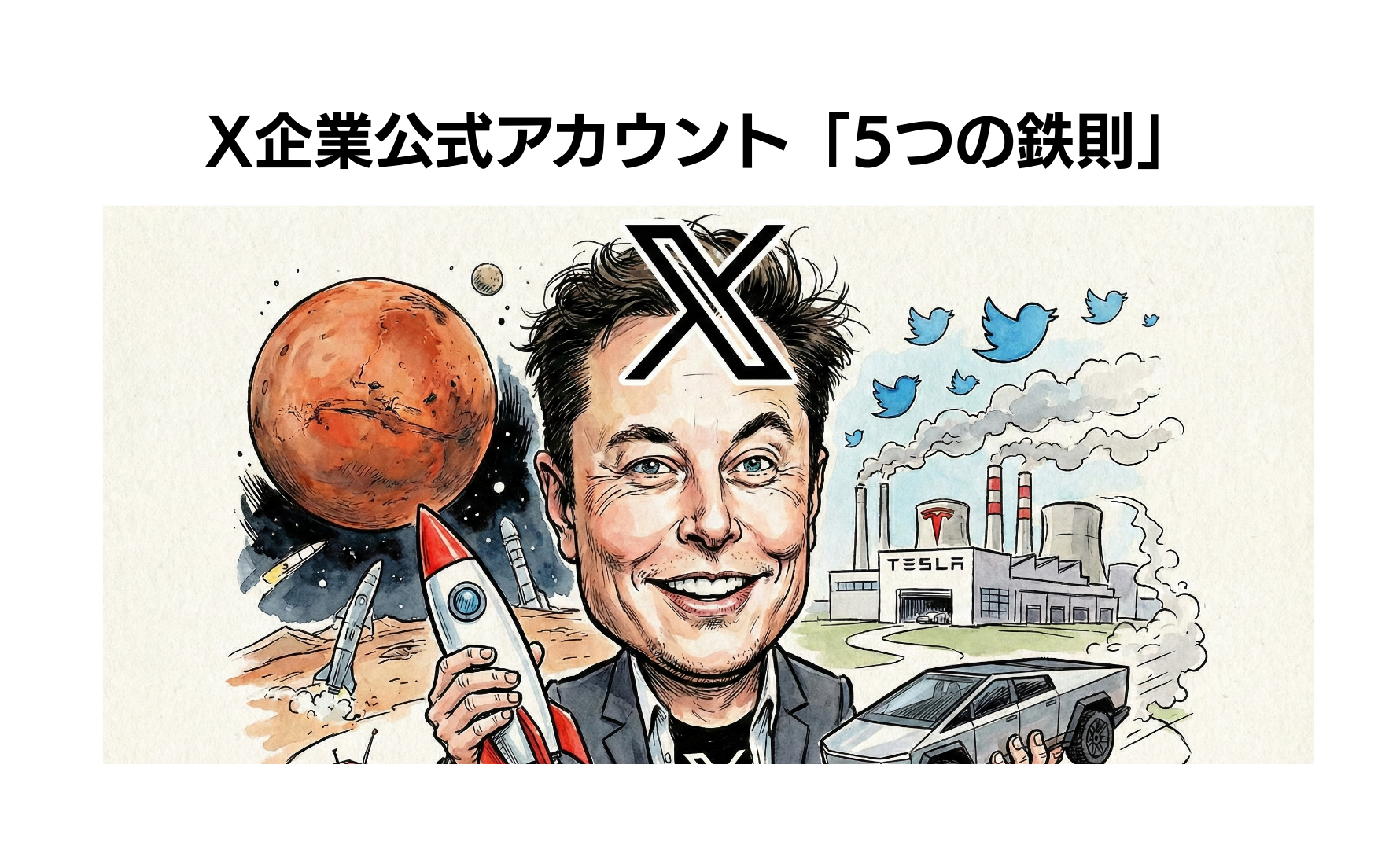産婦人科病院・クリニックのSNS発信のポイント

産婦人科病院の公式SNSアカウントの発信のポイント20選
当社は今まで多くの産婦人科病院やクリニックのホームページを制作し、SNSの運用の代行をしてきました。その経験の中から特に気を付けていることを20個選びました。昔はSNSというものはホームページに誘導する役割を示していましたが、今はSNSからホームページに行く人は少なくなり、SNSの中だけで完結するような構造にしなければいけません。
SNSを見たらその病院のすべてがわかるような情報発信が必要なのです。
参考になれば幸いです。
信頼感を第一にした発信
医療機関のSNSでは「親近感」よりも「信頼感」が最優先です。
誤った情報や過剰な演出は逆効果で、安心して相談できる印象が欠かせません。
医師や看護師の顔、院内の清潔さ、設備の透明な紹介を通して、誠実さを感じさせる投稿が患者の来院動機になります。
特に医師は顔出しを積極的に行った方が良いですね。
特に笑顔は大切です。
院長・医師の人柄を伝える
患者が産婦人科を選ぶ最大の決め手は「誰に診てもらうか」です。
院長や医師の考え方、診療スタンス、患者との関わり方などを定期的に発信することで、「この先生なら安心できる」と思われ、来院前の不安を軽減できます。
公式SNSではやり過ぎないことに注意しなければいけませんが、院長先生の趣味だったり、人柄が伝わるを発信するのもいいですし、妊婦さんに対してのメッセージなどを継続的に発信するのもいいでしょう。
安心感がを与えることができます。

出産・診療ストーリーの共有
出産体験談や、妊婦健診から出産・退院までの流れをわかりやすく紹介しましょう。
具体的なイメージを持たせることで「自分もここで出産したい」という感情が生まれ、集患につながります。
特に初産の場合は、自分がこれからどうなるのか?という不安を取り除くことが安心感に直結します。
やはり基本は、安心&感信頼感を重視した発信です。
写真・動画のクオリティ
医療機関は「清潔」「安心」「安全」が印象の要です。
暗い写真や雑な動画はマイナス印象になります。
自然光で明るい院内や笑顔のスタッフの写真(笑顔はとても大切です)、短いリール動画などを活用し、視覚的に心地よく伝えることで信頼と好感を両立できます。

院内設備・環境の紹介
最新の分娩台や個室、キッズスペースなどを写真で丁寧に紹介すると、患者が安心して選びやすくなります。
特に初産の方は「どんなところで出産するのか」を重視します。
設備の公開は「見えない不安」を解消する有効な手段です。
スタッフ紹介とチーム医療の姿勢
医師以外にも助産師、看護師、受付スタッフの紹介を行うと、温かみのある病院として信頼感が増します。
チームで支える姿を見せることで「安心して任せられる病院」という印象を与え、出産前の心理的不安を軽減します。
妊婦・ママ向けの生活情報発信
食事、運動、メンタルケアなど、妊娠・育児中に役立つ情報を定期的に発信することでフォロー価値が高まります。
患者は「相談できる病院」としての認識を強め、結果的に選ばれる確率が上がります。
教育的投稿は信頼の積み重ねです。

出産後のサポート体制紹介
母乳外来、産後ケア、メンタルケアなどのサポート体制を明示することは非常に重要です。
産後の不安は大きく、出産後も関係が続く安心感を与えると、口コミ・紹介につながります。
リピーターや友人紹介を増やす要となります。
給食画像
約1週間も入院する患者さんにとって、給食はとても大事な楽しみの一つです。
料理をおいしく撮影して、説明文には栄養士さんのコメントを掲載します。
コメントには各料理の栄養素やカロリーなどを明記します。

定期的な更新頻度
SNSが「止まっている」印象は、病院全体の印象を古く感じさせます。
週1〜2回のペースでも定期的に更新することで、信頼が維持されます。
最新情報を届けることで「今もきちんと運営されている」安心感を与えることができます。
フォロワーとの双方向コミュニケーション
コメント返信や質問募集を丁寧に行うことで、患者との距離が縮まります(コメントのやり取りは大勢の人が見ていますので、誠実な対応は病院のイメージ戦略に繋がります。)。
質問に誠実に答えることで「相談しやすい病院」という印象が定着し、予約や来院のハードルが下がります。
SNSは双方向メディアであることを意識し、コミニュケーションを大切にしましょう。

予約・問い合わせ導線の明確化
どんなに良い投稿でも、予約リンクが分かりづらいと機会損失になります。プロフィールに「24時間WEB予約はこちら」などの導線を固定し、投稿内にも定期的に誘導文を入れることが重要です。行動導線は集患の要です。
よくある質問(FAQ)の可視化
「初診時に何が必要?」「里帰り出産は可能?」など、患者の不安を先回りしてSNS上で解消すると信頼が高まります。
公式SNS上にFAQシリーズを投稿すれば、DM対応の手間も減り、患者満足度と業務効率の両立が可能です。
そしてFAQの充実はAI検索対策にとても重要な役割を持ちます。
患者の声・口コミ紹介
実際に利用した方の声を写真付きの実名(難しければ匿名)で掲載することで、リアルな安心感が伝わります。
口コミは最も影響力のある集患要素です。
医療広告ガイドラインを遵守しつつ「体験談」や「満足の声」を定期的に紹介すると信頼度が上がります。
イベント・教室・相談会の案内
母親学級、立ち会い出産説明会、ベビーマッサージ教室などの案内をSNSで発信することで、リアル接点が生まれます。
イベント参加は来院の第一歩になり、自然な集患導線となります。
オフラインの接点は信頼形成に最適です。

季節性とタイミングの意識
「インフルエンザ予防接種」「梅雨時の体調管理」「年末年始の診療案内」など、時期に応じた投稿は信頼される病院運営を印象づけます。
季節感のある発信は生活者目線を示し、フォロワーとの共感を生みやすくなります。
LINE公式アカウントとの連携
InstagramやXだけでなく、LINE公式アカウントと連携して「予約」「お知らせ」を一元化すると便利です。
LINEは患者の日常動線上にあり、フォロー後のリピーター化に強い影響力を持ちます。
SNS間連携は効率的な集患施策です。

ネガティブコメントへの誠実対応
誤解や不満のコメントに冷静で誠実に対応することは、他の閲覧者の信頼を得る絶好の機会です。
削除や無視よりも、真摯な姿勢で返信することで「信頼できる病院」という印象を生み、炎上リスクを防ぎつつ信用を積み重ねます。
参考記事:Googleマップの悪質コメント対処法と無料相談のご案内
医療情報の正確性と引用元明示
産婦人科に関する情報は命に関わるものも多く、信頼性が何より大切です。
専門家監修の内容や公的機関(厚労省・学会等)へのリンクを併記すると、専門性と安心感が両立します。
間違いのない発信がブランド価値を守ります。
投稿目的の一貫性
フォロワー数よりも「目的に合った投稿」が重要です。
「集患」「地域の信頼」「患者教育」など目的を一貫させることで軸がぶれず、内容の質が上がります。
テーマが一貫しているSNSは長期的にファン化・再来院を促進します。
創業25年の実績を持つ当社では、SNS運用代行の無料相談も行っております。
お気軽にご相談ください。