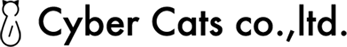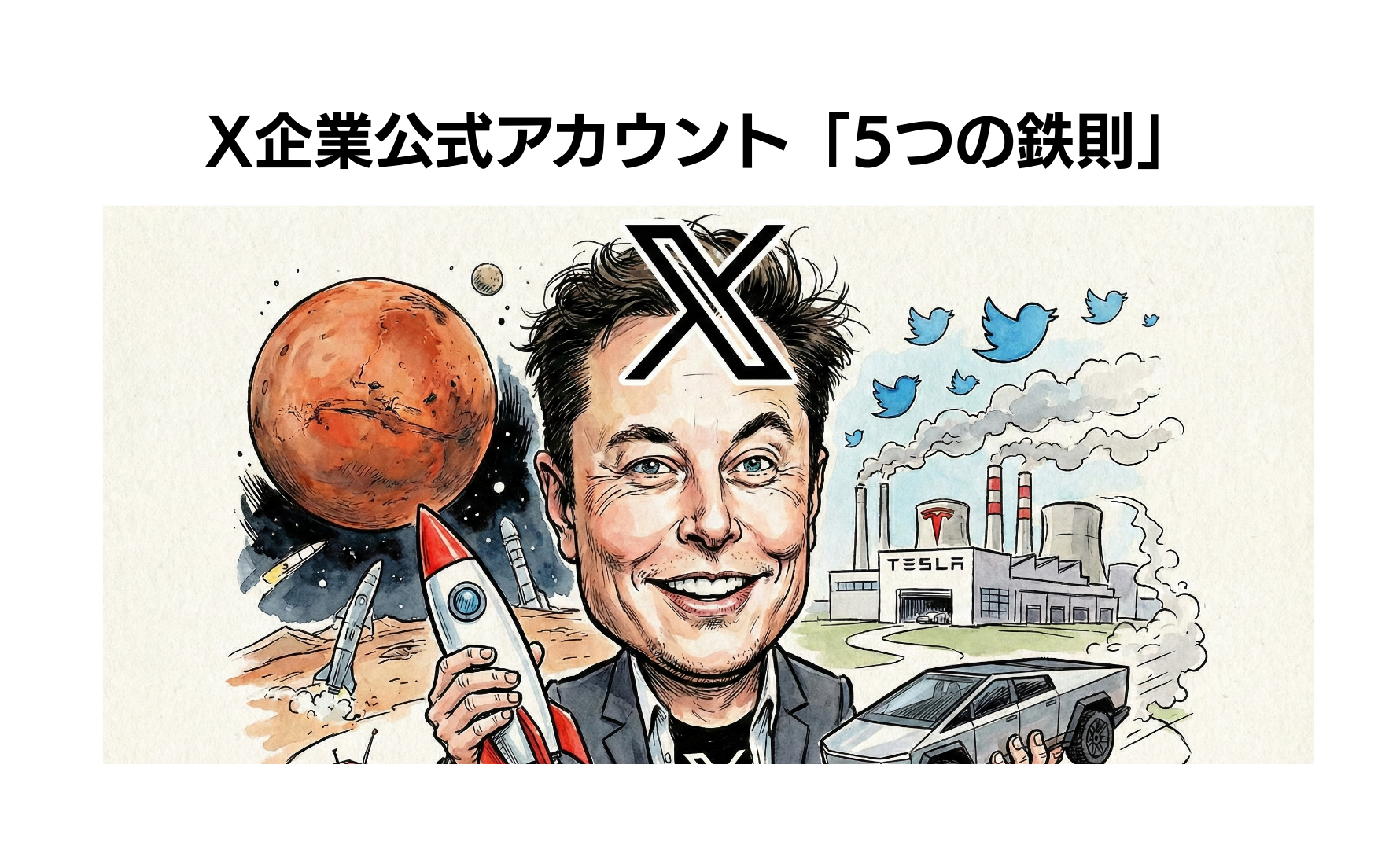訪問介護のホームページ制作のコツ

利用者家族に安心・信頼を与えるホームページ構成・デザイン・コンテンツ
株式会社CyberCatsでは多くの訪問介護のホームページを作ってきました。その経験から、訪問看護のホームページでこだわっていることを記事にしました。ご参考にしていただければ幸いです。
まず、ホームページ全体のデザインは高齢のご家族にも見やすく、温かみのある印象を与えることが重要です。介護・福祉関連のサイトを見るユーザーは不安や悩みを抱えている場合が多いため、文字は大きめでコントラストをはっきりとし、レイアウトは情報が整理されていて読みやすいものにします。配色は信頼感や清潔感を与える落ち着いた色を基調に、親しみやすさを感じるアクセントカラーを加えると効果的です。トップページのファーストビュー(第一画面)では、事業所が提供するサービス内容(訪問介護、高齢者対応、障がい者対応など)を一目で理解できるキャッチコピーや写真を配置し、「地域名+サービス名+特徴」のキーワードを盛り込んで訴求しましょう。例えば「■■市で高齢者と障がい者を支える訪問介護サービス」といったフレーズで、閲覧者に自分たちの求めるサービスだとすぐ伝わるようにします。
次に、家族の不安を和らげ信頼感を高める具体的なコンテンツ要素を充実させます。利用者やご家族は「大切な家族を安心して任せられるか」を重視するため、以下のような内容を盛り込みます。
スタッフ紹介ページ
介護スタッフや看護師の顔写真と氏名、資格や経歴を掲載します。スタッフの人柄や専門性が伝わるコメントも添えると良いでしょう。
実際にどんな人がケアしてくれるのか分かるだけで安心感が増し、資格・経験の明示によって「プロに任せられる」という信頼にもつながります。利用者と接するサービス提供責任者やヘルパーの紹介も充実させ、「訪問介護は人がすべて」であることを示すことで親近感と安心感を与えます。

施設・設備紹介
事業所の事務所やトレーニング設備、福祉用具などの写真を掲載し、サービス提供の環境が清潔で安全であることを示します。例えばバリアフリー対応や感染症対策の様子、緊急通報装置など安全対策についても説明しましょう。
単に設備の写真を並べるだけでなく、「この設備で何を解決できるか」「どのように安心・快適に過ごせるか」をわかりやすい言葉で補足すると、ご家族の不安軽減に効果的です。障がい者向けには、福祉車両や介助用具の紹介、重度障がいにも対応できるスタッフ体制など、対象者別の配慮が伝わる情報も盛り込みます。
サービス内容ページ
提供するサービスを高齢者向け・障がい者向けに分けて詳しく説明します。支援内容や対象者、利用条件を明確に記載し、「どのような悩み・ニーズに応えられるサービスか」を示しましょう。
複数のサービス(例:生活援助、身体介護、障がい者の移動支援など)を提供している場合はサービスごとにページを分け、1日の流れや具体的な支援例を写真付きで紹介すると利用者像を描きやすくなります。また利用料金や利用可能な時間帯、対応エリアなどの基本情報も隠さず提示してください。料金や空き状況をできるだけ明確に示すことはそれ自体が信頼感につながり、最新情報にアップデートすることで「運営がしっかりしている」という印象を与えられます。
基本理念・ごあいさつ
事業所の理念や代表者からのメッセージを掲載し(写真は絶対に【笑顔】です)、サービス運営に込める想いを伝えます。利用者本人や家族の悩みに寄り添う姿勢や、「地域に根ざした支援を行っています」「全ての人に笑顔を」などのモットーを示すことで、他社との違いを演出できます。(競合他社との差別化は大切です)
特に介護や障がい支援はデリケートな問題も含むため、誠実さや理念を語ることで「信頼できる事業所だ」という印象を持ってもらいやすくなります。

利用者・家族の声(口コミ)
実際の利用者やそのご家族から寄せられた感謝の言葉、利用して良かった点などのお客様の声を紹介できれば非常に効果的です。匿名でも構いと言ってるホームページ制作会社はたくさんありますが、ここは企業努力で実名で写真出しで利用者の声をいただきましょう。圧倒的に効果が違います。「スタッフが丁寧で安心できた」「困ったとき24時間対応してくれた」等の生の声は、新規の家族にとって安心材料となります。可能であれば写真付きのコメントや、利用者のビフォーアフターの様子(ただしプライバシーに配慮)を載せると信ぴょう性が増します。
情報発信(ブログ・お知らせ)
ホームページ上で定期的にニュースやブログ記事を更新し、事業所の日常の様子や専門知識を発信しましょう。例えば「イベントを開催しました」「熱中症予防の豆知識」など、日々の取り組みや季節の行事、介護に役立つ情報を載せます。サイト訪問者は事業所の雰囲気や活動状況を把握でき、運営の丁寧さが伝わります。複数回訪れたくなる仕掛けにもなり、閲覧者との信頼関係構築につながります。
また、よくある質問(FAQ)コーナーを設け、利用者や家族から寄せられがちな質問とその回答を掲載するのも有効です。「サービスを断られるケースはありますか?」「障がいのある家族でも対応できますか?」といった疑問への答えを用意しておけば、その場で不安を解消でき、安心して問い合わせや利用検討に進みやすくなります。またFAQは、AI検索対策にも有効なので、新規のユーザーに訴えたいことを盛り込むこともお勧めしています。
問い合わせ導線の明確化
サイトを訪れた家族がすぐ相談や予約ができるように導線を設計します。トップページや各ページの目立つ位置に電話番号や問い合わせフォームへのボタンを配置し、迷わず連絡できるようにしましょう。問い合わせフォームでは入力項目を最小限に留め、スマートフォンでもストレスなく送信できるUIにします。
また最近ではLINE等のチャットツールを問い合わせに使えるようにする施設もあります。高齢者のご家族向けには電話での連絡手段が特に重要なので、営業時間内の電話相談窓口の案内をはっきり提示しておきます。「24時間365日受付」のフォームや資料請求ボタンを設置すると、夜間でも問い合わせを逃さず受け付けられます。
以上をまとめると、家族に安心感を与えるホームページには、「どんな人たちがどんな想いで、どんな環境でサービスを提供しているのか」を具体的に示すことが肝心です。スタッフの顔が見えることや、日々の様子が伝わる情報発信は、それ自体で大きな信頼要素になります。高齢者と障がい者の双方を対象としている場合、それぞれに配慮した情報をバランス良く掲載し、誰にとっても「ここなら安心だ」と思える温かみと透明性のあるサイトを構築しましょう。
——————————
ケアマネージャーに紹介されやすい専門性・信頼感の演出
介護サービス利用を検討する際に大きな影響力を持つケアマネージャー(介護支援専門員)にも選ばれるホームページ作りが重要です。したがって、ケアマネージャーが見ても「この事業所なら信頼できる」「利用者に勧めたい」と感じられる情報を用意することがポイントです。
ケアマネージャーにアピールするには、まず専門性の高さや情報の充実を示します。ホームページはパンフレット以上に詳細かつ多彩な情報発信が可能なツールです。紙のパンフレットでは伝えきれない事業所の強みや取り組みも、Web上であれば写真・動画・テキストで豊富に伝えることができます。例えば対応可能なサービス範囲(高齢者のみならず障がい者も対象、医療的ケアの可否、認知症ケアの専門性など)や、スタッフの保有資格・研修歴、過去の事例紹介など、ケアマネが知りたい情報を盛り込みましょう。ケアマネージャー向けに特化したページを設け、「事業所概要・強み」「サービス提供体制」「加算取得状況」など専門的な情報をまとめておくのも有効です。「特定事業所加算取得済」「■■研修修了スタッフ在籍」といった記載は、サービス品質の指標としてケアマネに伝わりやすいでしょう。

スタッフの専門性・経歴の開示
前述のスタッフ紹介はケアマネ視点でも有用です。特にサービス提供責任者や管理者の経歴や、スタッフの人数と有資格者の割合などを掲載すると、「しっかりした人員体制で専門的なケアができる」とアピールできます。もし看護師や理学療法士等の医療職が在籍していればそれも記載し、利用者の状態悪化時の連携や重度障がい者ケアにも対応できる強みとして強調します。スタッフの研修受講状況も信頼材料です。「全ヘルパーが認知症ケア研修修了」「感染症予防に関する内部研修を毎月実施」など具体的に示すと、ケアマネ側も安心できますね。
専門情報や実績の発信
ホームページ上で、事業所が持つ専門知識を発信したり、利用者のケア実績例を紹介したりすることも有効です。ブログで専門的なノウハウを記事にすると、ケアマネにとっても有益な情報源となり得ます。また、具体的な成功事例を(プライバシーに配慮しつつ)紹介すれば、事業所の実力を裏付ける材料になり、信頼感アップにつながります。
ケアマネージャーに「この事業所なら任せられる」と思ってもらうには、専門性・情報の充実と透明性が鍵です。ホームページから事業所の強みや特色、サービス提供の具体像が掴めれば、ケアマネも利用者に紹介しやすくなります。実際、ホームページで丁寧に情報発信を続けてケアマネとのコミュニケーションのきっかけを作り、結果として紹介件数の増加につなげている事業所もあります。ケアマネ経由の利用者獲得には地道な信頼構築が不可欠なので、プロに選ばれるサイト作りを意識しましょう。
——————————
新規利用者(家族含む)獲得・Googleビジネスプロフィール
新規利用者やそのご家族にアプローチするには、ホームページ自体の集客力とコンバージョン(問い合わせ)率を高める施策が必要です。都市部では特にインターネット検索から情報収集する家族が多いため、検索エンジン対策(SEO)・AI検索対策・GoogleMAP対策と使いやすいサイト導線設計が重要になります。
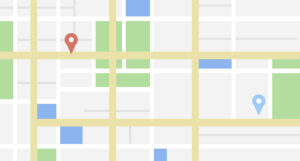
集客のためのSEO施策
介護サービスの集客におけるSEO戦略として、地域とサービス名を組み合わせた「地域名+サービス名」のキーワードでの上位表示が非常に有効です。また、ユーザーの検索意図に合わせたページ構成も重要です。「サービス内容」「事業所案内」「料金」など、関心ごとに情報を整理することで、サイト評価が高まり、問い合わせ率の向上につながります。
基本的なことですが、検索結果でクリック率を上げるため、メタディスクリプションには「地域密着」「無料相談受付中」といった魅力的かつキーワードを含む説明を記述すべきです。技術面では、スマートフォン利用者が多いため、モバイルフレンドリーなデザインや表示速度の最適化、セキュリティ(SSL化)対応といった基本的なSEO要件への対応が必須となります。
問い合わせ誘導の導線設計
サイトに訪れた潜在顧客をスムーズに問い合わせや見学予約まで導くことが目標です。各ページには明確な次のアクションを提示しましょう。例えばサービス内容ページの末尾に「サービスについて相談するお問い合わせフォームへ」というボタンを配置したり、画面上部に常時「電話相談」「資料請求」の固定バナーを設置したりします。また、一目で連絡先が分かるように、電話番号はヘッダーの目立つ箇所に大きく表示し、クリック一つで発信できるようにします(スマホの場合はタップで発信可能なリンクにする)。最近はLINEを使った問い合わせもニーズがあるため、「LINEで問い合わせ」ボタンを用意しておくと若いご家族層には好評です。
ユーザビリティの向上
訪問者がストレスなく情報に辿り着けるサイト構造も大切です。グローバルナビゲーション(メインメニュー)はシンプルに、「トップ|サービス内容|料金案内|事業所紹介|アクセス|採用情報|お問い合わせ」といった項目を用意すると分かりやすいでしょう。各ページへ迷わず移動できることが、ユーザー離脱を防ぎます。特に高齢者のご家族はウェブ操作に不慣れな場合もあるため、欲しい情報に1~2クリックで到達できる設計を心がけます。問い合わせフォームも入力手順が複雑だと途中で断念されてしまうため、項目は必要最小限にし、完了までのステップをシンプルにします(進捗バーなどを付けて「あと少し」であることを示す工夫も効果的です)。さらに、CTA(Call To Action)ボタンのデザインは目立つ色にし、「無料で相談する」「利用予約はこちら」など具体的な行動を促す文言を入れるとクリック率が上がります。
ローカルSEOと口コミ
地域密着の訪問介護事業所ならではの集客策として、Googleビジネスプロフィール(旧称: Googleマイビジネス)の最適化も行いましょう。これは株式会社CyberCatsでは特に重要視しています。事業所の営業時間や住所、写真、利用者からのレビューを充実させておくと、ローカル検索(地図検索など)経由の集客に役立ちます。ご家族が「■■市 訪問介護 おすすめ」等で検索した際、Google上で星評価や口コミが表示されるため、日頃から良い評価・レビューを集める努力も必要です。ホームページ上でも「利用者様の声」を紹介しましたが、Googleの口コミは第三者評価として信頼される傾向が強いので(AI検索対策にも重要です)、満足いただいた利用者家族にはレビューを書いてもらえるよう依頼するなど工夫しましょう(Googleの規定があるので気をつけてください)。
新規利用者獲得のためのホームページでは、検索で発見してもらい(SEO)、サイト内容で信頼してもらい(コンテンツ充実)、最後に迷わず行動してもらう(導線設計)という一連の流れを最適化します。介護業界では紹介や口コミが重要と思われがちですが、近年ではご家族自身がネットで情報収集し相談や見学につながるケースが増えているため、ホームページをしっかり作り込めば大きな集客力となります。小さな改善の積み重ねが地域の利用者との新たな出会いにつながるので、定期的にサイトを見直し、使い勝手や情報鮮度を保ちましょう。
——————————
訪問介護職採用情報ページの内容・構成と応募者に響くアピールポイント
人材不足が深刻な訪問介護業界において、ホームページの採用情報ページは貴重なリクルーティングの場となります。求職者が事業所のホームページを見ることで、「ここで働きたい」と思わせる情報を提供し、応募へ促すような構成・内容が求められます。以下に載せるべき内容とアピールポイントを整理します。

募集要項・求人情報の明示
まず、どんな職種で募集しているか(例:訪問介護員、サービス提供責任者、生活援助スタッフなど)をはっきり示し、具体的な仕事内容を詳述します。業務内容、1日の流れ、担当する利用者層などを具体的に記載すると応募者は働くイメージを持ちやすくなります。また勤務条件や待遇面も可能な限り透明に提示しましょう。給与、勤務時間、休日、勤務地などを明確にすることで、応募者は条件面での不安を解消できます。特に訪問介護はパート募集も多いため、正社員・パート各募集要項を分けて掲載しても良いでしょう。これら募集情報を丁寧に掲載することで質の高い求職者を引きつけ、ミスマッチを減らすことができます。(ページの序盤で給料を明記してしまうと給料だけで判断されてしまう可能性があるため、できるだけ募集要項は会社のアピールの後に書きましょう)
事業所の魅力・働く環境アピール
求人情報と併せて、「この職場で働くメリット」をしっかり伝えます。求職者が知りたいの「「この会社に勤めたら自分の将来はどうなるか」です。代表あいさつなどで会社の将来のビジョンを明確にしておきましょう。また「この会社はアットホームな会社」ですなどと書かずに、求職者に「この会社はアットホームな会社なんだ」と思わせなければいけません。この工夫は大事なので、制作会社と知恵を出し合って構成を練りましょう
現役スタッフの声・成功事例
応募者に最も響くのは、実際に働いている人の生の声です。ホームページ上でスタッフのインタビューや座談会記事、先輩職員から応募者へのメッセージを掲載しましょう。写真付きで笑顔のスタッフがコメントしているだけでも、親近感と職場の雰囲気の良さが伝わります。可能であればスタッフ座談会動画などを埋め込むと、よりリアルな声を届けられますが、難しければ文章と写真だけでも十分効果があります。現在働いている人の言葉は何より説得力があり、「自分もここで働きたい」というモチベーションを高めます。
——————————
創業25年の実績を持つ株式会社CyberCatsでは、新しくホームページ制作をご検討しているお客様に無料相談も行っております。
お気軽にご相談ください。