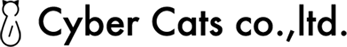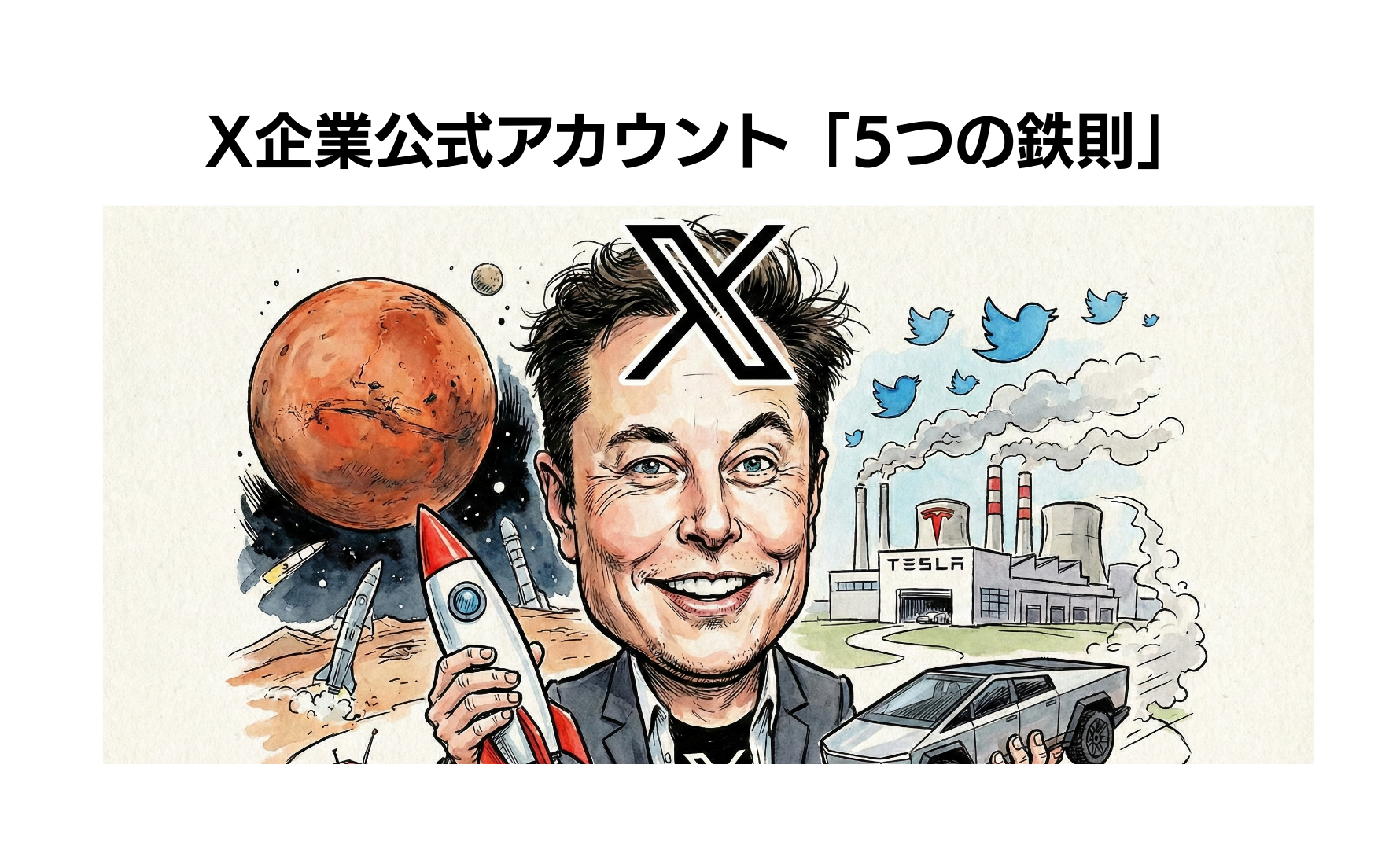産婦人科病院・クリニックのホームぺージ制作のポイント

産婦人科病院の集患を目的としたホームページ設計・気をつけたいこと20選
当社は今まで多くの産婦人科病院やクリニックのホームページを制作してきました。
その経験の中から特に気を付けていることを20個選びました。
参考になれば幸いです。

予約導線の一元化と強調
ファーストビューに「24時間Web予約」と「電話の固定ボタン」「問い合わせフォーム」を配置します。
ユーザーがいつでもコンタクトできるようにするためです。
ホームの入力項目は最小限にし、安心して予約できる体験を担保します。
診療時間・アクセスの即時可視化
ヘッダー直下に本日の診療時間、休診、夜間体制、地図と駐車場、最寄駅からの所要を一目でわかるようにします。
初見ユーザーの「行けるか」不安を最速で解消し、比較検討段階から来院意思決定へ素早く進める必要があります。

診療メニューの整理と差別化
産科・婦人科・健診・不妊・無痛分娩などを患者視点の言葉で体系化します。
対象者や適応、流れ、所要時間、費用の目安を並記するとよいでしょう。
自院の強みと他院との差異を具体に示すことで、目的来院の迷いを減らし、ニーズ一致の患者を確実に案内できます。
医師・スタッフの顔と専門性
院長・各医師の顔写真、経歴、専門領域、学会認定、年間症例、メッセージを掲載します。
メッセージは特に妊婦目線で心に刺さる言葉を選びます。
助産師や小児科連携も明記。
「誰に診てもらえるか」は病院選びの核心になります。
人柄と実績を可視化し、信頼と安心感を高め、予約完了までの心理的ハードルを下げることが必要です。

費用の透明性(分娩費含む)
分娩費用の目安、無痛オプション、検査ごとの料金、支払い方法、出産育児一時金・自治体助成の扱いを具体に。
見積もり例や入退院時の支払タイミングも明記します。
費用不安は最大の離脱要因。
早期に解消することで意思決定を力強く後押しする。
安全・救急体制の明記
合併症対応、帝王切開体制、周産期センター/NICUとの連携、夜間当直、感染対策を分かりやすく。
リスク時の搬送プロトコルも示します。
「もしもの時」を具体で伝えるほど、初産婦や高リスク妊婦の不安は和らぎ、安心が予約行動に直結することが必用です。

写真・動画での院内体験の可視化
病室・分娩室・LDR・面会スペース・食事例を、清潔感ある写真と短尺動画で紹介します。
少しハードルが高いですが、360°ツアーも有効です。
文字より速く「雰囲気」を伝え、想像と現実のギャップを縮めることを心がけましょう。
視覚情報は安心と期待を同時に高め、見学→予約の転換を促すことに有効です。
患者の声と評価の適切な活用
体験談は医療広告ガイドラインに配慮しつつ、当院への期待や改善点を要約して掲載します。
外部口コミの傾向も統合し、誠実なフィードバック対応を示す。
第三者の視点は信頼の補強となり、比較検討段階の背中を押すソーシャルプルーフになる。
この時大事なことはできるだけ顔写真載せていただき本名でコメントをもらいましょう
これができれば圧倒的な信頼感を獲得できます。

不安解消のためのQ&A/判断フロー
「出血がある」「胎動が少ない」など症状別に「受診目安」を図解しましょう。
受診の緊急度、自己対応、連絡先も明確化します。
初産婦の検索意図に合致し、検索流入と適正受診を両立。
不安を減らす体験は、そのまま好意形成と選択確度の向上に繋がります。
またQ&AはAI検索対策にも非常に有効ですので、詳しくは当社にお問い合わせください。
ローカルSEOとGoogleビジネスの整備
病院名+地域名、症状名+地域名で上位表示する構造化データとNAP(Name, Address, Phone Number)統一を徹底します。
Googleビジネスで診療時間・写真・投稿を最新化。(こまめに更新しましょう)
地図検索の露出が来院の起点となります。
ホームページと地図の一貫表示で、認知から予約への導線を滑らかにすることが大切です。
スマホ最適化と高速表示
患者の大半はスマホ閲覧します(95%と言われています)。
フォント、指で押しやすいボタン、遅延読込、画像最適化で3秒以内表示を目標にします。
回線が不安定でも迷わず予約できる体験が、広告より確実にCVR(コンバージョン率)を上げ、離脱率を下げます。
速度はそのまま信頼感にも直結するので重要です。

法令・ガイドライン遵守と信頼表示
医療広告ガイドライン、個人情報保護、クッキー同意、常時SSLを明示します。
誇大表現や体験談の扱い、根拠となる認定・実績の出し方を整理します。
第三者認証やセキュリティバッジを適切に掲示し、「安心して任せられる医療機関」を形式面でも証明しなければいけません。
分娩予約状況・待ち時間の可視化
分娩予約の空き枠、外来の混雑予測、待ち時間目安を簡易に提示しましょう。
満床時の近隣連携や次善策も案内します。
「予約できるか」が早く分かるほど、無駄な問い合わせが減り満足度も向上します。
患者・スタッフ双方の負担を軽減し体験品質を高める効果もあります。
緊急時の連絡手順と夜間体制
夜間・休日の連絡先、症状別の受診基準、持ち物、来院時の入口や駐車場の案内を固定表示します。
迷いなく正しい行動を取れる導線は、患者安全と業務効率の両方に直結します。
家族が見ても分かる平易な表現と、常時最新の更新が重要となります。
産前産後クラス・支援の案内
両親学級、母乳外来、骨盤ケア、育児相談、産後ケア事業などをカレンダーで見やすく表示。
マタニティービクスを取り入れている場合は、実施している画像も載せましょう。
各サービスの申込方法や持ち物、対象週数も明記します。
出産以外の接点を増やすことで継続的な関係が生まれ、口コミや再来院、家族の受診へと自然に広げることが狙いです。
もちろん公式SNSでも発信し、露出を上げます。

コンテンツ設計(週数別・症状別)
妊娠週数ごとの過ごし方、健診スケジュール、検査の意味、婦人科の症状解説を患者が解りやすい言葉で掲載します。
検索ニーズを捉え内部リンクで次の行動へ導く事も重要です。
専門性を「やさしく翻訳」した記事は、信頼獲得と自然検索での集患を同時に実現できます。
SNS・LINE連携と情報の一貫性
InstagramやLINEで院内の雰囲気やお知らせを発信し、予約や詳細は必ずサイトに還流します。
ブログ記事も有効です。(当社ではAI検索対策に有効なブログの書き方もご指導しています)
投稿とサイトの内容・トーンを一致させ、最新情報の更新責任を明確にします。
日常的な接点の積み重ねが、いざという時の第一想起につながります。
オンライン相談・問い合わせの整備
問い合わせに対するレスポンスを早くすることを心がけましょう。
よくある質問は即時回答、個別相談は翌診療時間に返信します。
写真添付や既往歴入力も簡単に。
電話が苦手な層の不安を早期に解消し、来院前の壁を下げます。
対応範囲と返信ポリシーも明確にしておくことは重要です。

読みやすさ・アクセシビリティ・多言語
やさしい日本語、ふりがな、音声読み上げ対応、コントラスト確保、英中韓の要点ページを用意します(できれば)。
妊婦や高齢者にも見やすいUIは全員の使いやすさに直結し、情報弱者を取りこぼさない姿勢が、地域での好感度と推薦につながります。
計測と継続改善(PDCA)
タグで予約完了や電話タップを計測し、離脱箇所を特定。
ABテストでコピーやボタン配置を検証。
検索語やFAQのログを施策に反映。
作って終わりにせず、データで「患者のつまずき」を継続的に解消する設計が長期的な集患を支える。
創業25年の実績を持つ当社では、新しくホームページ制作をご検討しているお客様に無料相談も行っております。
お気軽にご相談ください。